中央区の新築一戸建て仲介手数料無料!!
|
|
|
| |
|
|
いい家めぐり愛 |
|
|
|
|
|
| |
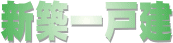 |
|
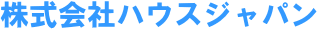 |
|
 |
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
http://www.77japan.com/baibai
|
|
戻る |
|
戻る |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
中央区の歴史・観光
|
|
住まい探しを始める準備の一つとして、これまで住み続けてきた家の建替えや、其々の地域に土地勘のある方は別として、新たに新築一戸建て購入を考えている方の前情報として、その地域の歴史や先人たちの日々の暮らしぶり、そして、住環境等を知っておくことも大切なことだと思います。
そのため、各地域ごとに先人達の足跡を調べられる限り書き綴ってみました。
少しでも家探しの参考にしていただけると幸いです。 |
|
| |
|
|
◆歴史探訪!
およそ3万年~1万2千年前のころから与野の大地に旧石器時代人が現れ、生活をしていたことが、市内12ヶ所の旧石器時代の遺跡によって明らかになってきました。
このように与野の台地上に石器だけを使用した人びとがいたことが確かとなり、更に市内2ヶ所の遺跡からは炉跡も発見されましたので、これらの人びとが火を使っていたことも明らかになっています。
今からおよそ1万2000年位前になると、人びとが石器のほかに粘土を焼いて作った土器を使用した縄文時代が始まります。
昭和32年4月に発掘調査が行われ大戸貝塚では、東西約35メートル、南北30メートルに及ぶ、竪穴住居跡1軒の存在が確認されています。
この貝層から発見された貝はヤマトシジミ・オキシジミ・ハマグリ・アサリ・カキ・ハイガイなど16種類にも及んだそうです。その他に、鹿角1、タイ骨1、犬の骨なども見つかり、縄文前期の人々の食生活の一端をうかがい知ることが出来ます。
“どれも天然物ばかり!!当時の人は 相当のグルメだったんでしょう~ね~” (@_@;)
この様に、遺跡の西側の崖下には海水が入り込んでいた鴻沼低地が広がっていますから、大戸の貝塚人は、貝や魚を中心とする海の幸やシカ・イノシシ・木の実などの陸の幸を食べ、小さな竪穴住居に入って相変わらず移動生活をいたものと思われます。
2100年位前から弥生時代に入り、これまでの縄文文化と著しく異なっている点は、朝鮮半島を経由して、新しい青銅器や鉄器などの文化が伝わってきたことです。
水田に種籾を播き、米を作るという稲作技術が伝わってきました。
そのほか水や物を貯蔵するための壷・煮沸するために用いた甕・食物類をのせる脚付の皿といわれる高杯・食物類を蒸すための器なども出土しており、当時すでに水稲耕作が行われていた事実を証明できるような新しい土器や石器が発見されています。
市内の代表的な遺跡として注目されるのが、中里前原遺跡です。この遺跡は大戸小学校の北側およびその周辺にあり、昭和53年2月1日から28日にわたって第一次の発掘調査が行われたそうです。
この遺跡は、縄文と弥生時代の遺跡が重なり合っている複合遺跡になっているそうで、発掘した範囲内だけでも弥生後期の住居跡が12軒も発見されたそうです。
そして、この多くの住居跡を取り囲むようにV字形の壕が二条、箱形の壕も一条発掘されたそうです。
これらの遺跡とそこから発掘された遺物により弥生後期の人々の暮らしぶりをかなり鮮明にとらえることができます。
この辺り一帯は鴻沼があり日当たりもよかったので、当時も大変暮らしやすい場所であったようです。
鴻沼低地をのぞむ与野支台や浦和・大宮支台と呼ばれる台地に古墳時代の遺跡も数多く発見されていますので、縄文・弥生の時代に引き続き、古墳時代にも多くの人々が集団で暮らしを立てていたことが明らかになってきたようです。
奈良時代の遺跡として、上峰遺跡、寺田遺跡発見されています。
平安時代の遺跡としては、八王子前原遺跡、曲庭遺跡、南上峰遺跡が発掘されています。
鎌倉時代のもので、与野市下落合の地には南北に延びた赤土層からなる台地があり、そこには遠い昔から「氷川大明神」、あるいは「笠守さま」とよばれ、村人たちから尊崇され、親しまれていた鎮守があります。
近世初頭の近郊一帯は、与野領・浦和領・植田谷領・忍領・岩付領など34の領からなっていました。
たとえば与野領には1町22か村があったそうで、領名は中心的な集落であった与野から起こったものだそうです。
そして与野市域の与野町・上落合村・下落合村・中里村・大戸村・上峰村・鈴谷村それに小村田村は、与野領に入っていましたが、円阿弥と八王子の両村は当時植田谷領に属していました。
本町通りを中心とする与野町は室町時代のころから市場の町として栄え、江戸時代に入ると相模・甲斐の二国から奥州方面への人馬の継立場として、また商品物資の集散地として、重要な役割を果たしていました。
町並みは「新編武蔵風土記稿」によれば、江戸からの行程七里(約28キロメートル)の位置に当たり、家数も304軒と浦和宿(208軒)・大宮宿(200余軒)に比べ多く「道の左右軒を連ねたること、あたかも都下の町に似たり」とも記されています。
往還(本町通り)を三分し、その区切りごとに石の地蔵を建て、北の地蔵から以南を上町と呼び、その次を中町、さらにその南を下町と呼んでいました。
そのうち中町は、長さ九町ほどもあり、道の両側には大きな商家が軒を連ねていたそうです。
1830年に御鷹場内で、鉄砲打ちをした戸田渡船場の船乗り、渡世の留五郎の供述書には、浦和宿・大宮宿・与野町の商人荷物やそのほかの村の雑穀・芋ならびに野菜物を船積みし、江戸表へ運び、江戸からは宿場や村々商人の仕入れ荷物を積んくることを生業としていると書いてるそうです。
これらのこと等により、与野町の商人が戸田河岸を経由して江戸と物資の交流をしていたことが明らかになっています。
このように、江戸時代の与野町は、この近辺の農村と江戸との物資の売買取引の中継地として市場が月六回開かれ、すこぶる繁盛していたようです。
昭和33年には単独で市制を施行しました。
昭和44年に新大宮バイパスが縦断し、加えて昭和60年にはJR埼京線が開通し、北与野駅・与野本町駅・南与野駅の3駅が開設されました。
平成12年に「さいたま新都心」の街びらきが行われ、平成13年5月1日には浦和市・大宮市・与野市が合併し「さいたま市」が誕生しました。
さらに平成15年4月1日の政令指定都市移行に伴い、9行政区のひとつとして中央区が設置されました。
そして現在、さいたま新都心駅や、その西側の最寄り駅である北与野駅周辺には、さいたまスーパーアリーナや高層ビル郡が立ち並んでいます。
空気の澄んだ日に近隣から望む、照らしだされたビル郡の夜景は絶景です。
与野本町駅西側にある「彩の国さいたま芸術劇場」では国際的に評価の高いコンサートや舞台が催され、蔵造り住宅など江戸の面影を残す与野本町の景観とともに「芸術・文化創造発信の地」となっています。
◆観光スポット!
与野の観光案内
|
|
|
|
|
Copyright (C) All Rights Reserved by 株式会社ハウスジャパン
埼玉県さいたま市桜区道場2丁目9番5号 |
|
|